漢字
工
- IPA
 kuŋ
kuŋ
- ????
 kung
kung
- ??
 古紅切
古紅切 見
見 平声
平声 公
公
- ????
 ク
ク コウ
コウ
- ???
 東
東
- ????
- ??
 工
工 gōng
gōng 常用漢字
常用漢字 開口一等韻
開口一等韻
- ???
 たくみ#4
たくみ#4 攻
攻 紅
紅
- ??
 工
工 通
通 東
東
- 表示
 U+5DE5
U+5DE5 工
工
??
書体
- 楷書

- 篆書
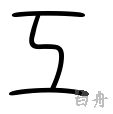
- 隷書
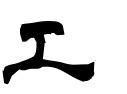
- 行書

- 草書

古代文字
- 古代

参考文献:::工
- 注解
- *1飾拭古今字。又部曰。㕞、飾也。巾部曰。飾、㕞也。聿部曰。𦘔、聿飾也。彡部曰。彡、毛飾畫文也。皆今之拭字也。此云巧飾也者。依古文作?爲訓。彡者飾畫文。巧飾者、謂如㡪人施廣領大袖以仰涂而領袖不污是也。惟孰於規榘乃能如是。引伸之凡善其事曰工。見小雅毛傳。
- *2直中繩。二平中準。是規榘也。
- *3?有規榘。而彡象其善飾。?事無形。亦有規榘。而?象其㒳褎。故曰同意。凡言某與某同意者。皆謂字形之意有相似者。古紅切。九部。
- 備考
- #1巧飾なり、人の規榘(きく)有るに象るなり、巫と同意、凡そ工の屬は皆な工に従ふ。(????)
- #2工具の形。説文に「巫と同意」とあるが、巫のもつところは、神事に用いる呪具。工具の工は、金文に鍛冶の台の形にみえるものがあり、巫祝の用いるものとは異なるもの。ただその形が似ているので、のち通用するに至ったのであろう。虹・空・江の工は中空で彎曲する形のもの。金文の工にも、下の画を彎曲した形に作るものがある。巫祝・工具の工とは、また別系である。(??)
- #3上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。(???)
- #4工(たくみ)。技巧の習熟した職人。工作者。
- #5巫項
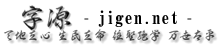
 コウ
コウ 工
工
