山田方谷
幕末、明治初期の儒学者。
松山藩で藩政改革を断行、貧乏板倉と呼ばれた藩は見事に再生し、民心・風俗を一新させた。
その治績は旅人が領内に一歩入るとすぐに分かる程であったという。
- 生誕
 岡山県
岡山県
- 所属
 松山藩
松山藩 岡山県
岡山県
- 生年
 1805年
1805年
- 没年
 1877年
1877年
述懐
父兮生我母育我。天兮覆吾地載吾。身爲男兒宜自思。苶苶寧與草木枯。慷慨難成済世業。蹉跎不奈隙駒驅。幽愁倚柱獨呻吟。知我者言我念深。流水不停人易老。鬱鬱無緣啓胸襟。生育覆載眞罔極。不識何時報此心。
父や我を生み母や我を育つ、天や吾を覆ひ地や吾を載(の)す。身は男児たり宜しく自ら思ふべし、苶苶(でつでつ)なんぞ与(とも)にせん草木の枯れるを。慷慨(こうがい)成し難し済世(さいせい)の業、蹉跎(さた)いかんともなせじ隙駒(げきく)の駆けるを。幽愁(ゆうしゅう)柱に倚(よ)り独り呻吟(しんぎん)す、我を知る者は言ふ我が念深しと。流水停(とど)まらず人老い易し、鬱鬱(うつうつ)縁(よ)る無し胸襟(きょうきん)啓(ひら)くを。生育(せいいく)覆載(ふうさい)真に極まりなし、識(し)らず何の時か此の心に報いん。
父母は私を生育し、天地は私を覆載(ふうさい)してくれる。だから男児として生まれた身なればこう思うべきなのだ、どうして茫然として草木の枯れると同じくしようか、と。心は昂ぶるばかりで済世(さいせい)の事業は成し難く、志を得ないまま月日はあっという間に過ぎてゆく。深き憂いを柱の陰で独り呻吟(しんぎん)すれば、私を知る者はいう、考えすぎなのだ、と。だが水の流れは止まらず人の老いもまた待つことはない、それを思うと私の心は鬱蒼として沈んでしまうのだ。でも天地万物の本質は真に極まり無し、されば自然とこの心に報いる時がくるのだろう。
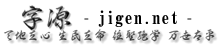
 山田方谷を印刷する
山田方谷を印刷する